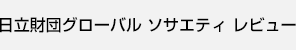多文化共生を刷新する
――共に生きるための「安全なスキマ」を拓く
1.多文化共生とは
1)多文化共生の陥穽
多文化共生社会とは,「国籍や民族などの異なる人々が,互いの文化的ちがいを認め合い,対等な関係を築こうとしながら,地域社会の構成員として共に生きていくこと」である(総務省 2006)。文化人類学者として日本における多文化共生に関する議論を牽引してきた栗本英世はその歴史性について以下のように述べている。
「多文化共生」という日本語の概念は,1990年代前半に使用されはじめ,1995年の阪神・淡路大震災を契機に一般に広まり,多数の地方自治体,学校や市民組織がその実現に取り組むようになった。こうした努力の結果,エスニックなマイノリティの人たちがより可視的な存在になり,社会のなかで人間らしく生きていける空間が増大した。このことの意義はおおきい。21世紀に入ると,日本政府がこの概念を正式に取り上げ,さまざまな大学に多文化共生の名前を冠した学科やコースが設立された。(栗本 2016:69)
近年,多文化共生は,人類学や社会学をはじめとして学術界においては批判にさらされている。栗本もまた,多文化共生の概念における「文化」の射程が狭すぎることが導く脱政治化や,マジョリティとマイノリティの関係における脱歴史化について鋭い考察を加えている。社会学者の岩渕功一は,『多様性との対話 ダイバーシティ推進が見えなくするもの』を編集し,多様性やダイバーシティ推進によって不可視化される問題について多様な事例を用いて論じている。少なくとも多文化共生やダイバーシティについて論じる研究者間において,これらの概念を無邪気に善きものとして捉える研究者はいないといっても過言ではない。
2)国際社会は日本をどうみているか
しかし一方で,多文化共生という概念が社会にもたらす豊かさの可能性は大きい。
それはどのような可能性か。その可能性を探るためには,日本が国際社会においてどのようにみられているかが役立つだろう。
ノルウェーのアンネシュ・ブレイビクは,多文化主義が推進されることへの警鐘を鳴らすために,2011年7月22日,77名の命を奪う人類史上最悪の大量殺害事件を起こした。ブレイビクは,日本を多文化主義から最も遠い社会として理想化し,麻生太郎首相(当時)に会いたいと手記を残しており,事件後の精神鑑定には,日本人医師を希望していたことが明らかになっている。遠い北欧の人類史上最悪の大量殺害事件を起こした犯罪者が,日本社会とは,多文化主義/多文化共生を拒否している社会であるとして認識していることを,日本で暮らすわれわれは深刻に受け止めなければいけない。
さらに,欧米メディアが頻繁に取り上げるように,日本における性差別主義は国際的にも悪名高い。2023年に発表されたジェンダーギャップ指数では,日本は過去最低の146か国中125位となった。最も深刻である政治参加の評価では,女性の占める割合が,衆議院議員では10%(閣僚では8.3%)で138位である。収入や企業の役員・管理職の割合での平等も進まず,経済分野は世界123位となっている。政治や経済といった最も重要な領域において女性の代表性を高める必要はいうまでもないが,人数を増やすだけで解決することは難しい。世界各国のメディアがこぞって報じたように,東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の会長を務めていた森喜朗元首相は,自身の組織委員会に属する女性たちを「わきまえておられて」と発言した。森元首相の言葉や,ジェンダーギャップ指数に表れているとおり,政治や経済の領域で女性の代表性が極めて低く,根強い家父長制に根差した社会である日本では,「わきまえる」女性しか,男性中心主義的な構造に入り込むことを許されていない。
日本におけるジェンダー状況の異常さは,主として女性が被る性暴力の扱い方にも表れている。内閣府男女共同参画局は,2022年6月17日,全国の若者(16~24歳)を対象に実施した,性暴力被害に関する初の実態調査の結果では,対象者6,224人のうち1,644人(26.4%),約4人に1人が何らかの性暴力被害にあったことがあると回答した(内閣府男女共同参画局 2022)。こうした実態があるにもかかわらず,日本では「レイプ神話」(性暴力に対する誤解と偏見)も根強く,また,被害者のケアのシステムも不十分である(Osawa 2023)。
ブレイビクが日本を最も多文化主義から遠い社会であるというように,また,各データや報道が明らかにするとおり,性暴力や性差別主義を払しょくできない社会である日本は,今後の社会的発展のためにも,解決しなければならない多くの課題を抱えている。
このような背景において,やはり希望を見出すことができるのは多文化共生の視点であろう。総務省による多文化共生社会の定義にジェンダーの視点は含まれていないが,それでも,「互いの文化的ちがいを認め合い,対等な関係を築こう」という表明には,従来の均質的なイメージをもつ日本社会をさらに豊かに刷新する契機を見出すことができる。多文化共生という概念やその実現のためには,数多くの落とし穴が内包されていることは認めなければならないが,女性や子ども,マイノリティといった政治経済的に疎外されている人びとにとってこのムーブメントが極めて重要であることを繰り返し確認したい。
本稿では,カナグスク金城馨さんのインタビューを参照しながら,多文化共生の視点が内包する落とし穴をあぶりだし,多文化共生をよりインクルーシブで素敵なものにするための回路をみいだしてみたい。マイノリティの側からこの現象を眺める時,この概念がもたらす負の側面が浮かび上がる。「異なる人々」という記号化や「文化的ちがい」によってある集団を徴づけることには,「言語創造」の契機となる側面と,同時に「言葉の牢獄」をもたらしうる側面がある。特に後者による弊害は,そうして記号化される一人ひとりの傷や経験を代替可能なものとして顔や声を非人称化させることにもつながる(石原 2022)。こうした課題を克服するにはどうすればよいだろうか。次節では多文化共生の落とし穴を確認したい。
2.多文化共生の落とし穴
1)ブラック・ライブズ・マターに学ぶ多文化共生の問題点
ダイバーシティ推進は,「様々な差異をもった人々の存在をこれまで以上に可視化しているし,差別・不平等に苦しむひとたちを力づけ,その解消に取り組む実践を伴っている場合もあるだろう」と評価される部分である一方で,「制度化・構造化された不平等,格差,差別の問題を後景に追いやり,その問題の解消に継続して取り組んでいく必要が見失われてしまいがちになる」ということに警鐘が鳴らされている(岩渕編 2021)。かつてテッサ・モーリス=スズキが「コスメティック多文化主義」という言葉を提唱したとおり,「うわべだけの」あるいは「見せかけの」多文化主義は3F―ファッション,フェスティバル,フード―といったマジョリティの暮らしを変更せずに済むもののみを称揚し,マジョリティとマイノリティの関係性を必ずしも対等なものにする回路がないということは重要だ。
3Fのような,多数派にとって罪悪感や暮らしの変化を喚起させないうわべだけの多文化主義は,先住民やレイシズムの対象となるような民族・人種的マイノリティ当事者にとっては,権利回復を遠ざけてしまう。
互いの多様性を尊重し,一人ひとりの能力が発揮されている状態について近年ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)という言葉が登場している。日本特有の言い回しである多文化共生もまた,同様の視点を持つものであり,そこに英語圏で標準的に使用される多文化主義もつらなっている。D&Iはマイノリティにとって必ずしも課題解決につながらないという指摘をみてみよう。
D&Iは,BLM1の(あるいは人種に関するあらゆるムーブメントの)隠れ蓑にはならない。人種差別は,真正面から取り組まなくてはならないのだ。D&Iの中の取り組みの一つとして論点をぼやかしてしまうと,我々は本腰を入れて立ち向かうべき課題から逃げることとなる。BLMは耳に心地よい話題へとトーンダウンしてしまい,現状を打開することができなくなってしまう。
2023年にOLIVER’s UK GroupのCEOに就任したアミナ・フォラリンは,異なる文化を持つ人びとや多様性を理解しようということを意味するダイバーシティが,必ずしも人種差別の解消につながらないことを述べる。BLMは,「制度的な人種差別や不平等だ。これは具体的には,他の人種には与えられるさまざまな機会が,黒人には与えられずに排除されることを指す。過小評価され,支援を受けられず,制度から漏れ落ちることの多い彼らが成功を収めるためには,より多くのサポートが必要なのだ」といい,さらに,ビジネスの場において人種差別や不平等の解消が極めて困難であることも説明されている。
この視点を用いて,カナグスク金城さんのインタビューを参照すると,日本における多文化共生の現在も浮かび上がる。
(中略)沖縄に対する日本人のまなざしは沖縄が遅れている,野蛮・未開であるというものでした。
これは明らかな差別であり,跳ね返さなければいけないのですが,大阪の人たちは大阪弁ですから,沖縄から来た青年たち一人一人は大阪弁は習っていませんし,それを跳ね返すだけの言葉を使うことができずコミュニケーションや会話がうまくいきません。
日本社会における沖縄人に対する身体的差別の度合いは弱まっているとは思います。沖縄人に差別していませんと言う日本人が増えてきて,「私は沖縄が大好きだ」,「沖縄はすごい」と,褒める人もいます。そのような中ではやはり解決していない問題があります。自分たちが受けた差別の当事者である日本人,日本社会が差別をやめようとしないことの中で,自分たちはそのことの問題をずっと提起し続けなければいけないという感覚があります。
(カナグスク金城さんのインタビューより)
カナグスク金城さんのインタビューからは,多文化共生の視点において,マジョリティがマイノリティを一方的な枠組みにおいて包摂することには暴力が潜むことを示している。差別や不平等が起こったときに,劣位に置かれた集団が異議申し立てを行うことのみではその解消は難しい。さらに,「沖縄が大好きだ」「沖縄はすごい」といった表面的な包摂は,ひるがえって根本的な暴力構造をみえなくしてしまう。それは一人ひとりの振る舞いが非倫理的であるということではない。責任を個人化することでは,多文化共生がもつ可能性をつぶしてしまうだろう。大切なことは,不備を少しずつ調整していくことである。次節では,そのための鍵概念であるマジョリティの特権性に関する議論をみてみたい。
2)特権性の自覚が拓く多文化共生
マジョリティ特権の議論を日本で率いてきた出口真紀子は,特権とは,「あるマジョリティ側の社会集団に属していることで労なくして得る優位性」であるという(出口 2021)。以下では,出口による特権性の議論から,多文化共生の実現において何が重要であるかを提示したい。
出口は,私たちはマジョリティ性とマイノリティ性を両方もちあわせ生きているが,民族・人種,学歴,アビリティ(障害),ジェンダー,セクシュアリティ,階級,都市か地方か,などにおいてマジョリティ性が多いほど自分の特権に気がつかないという。分りやすい例は,公共の乗り物に乗るときに健常者は自分の都合のよい出入口を利用できるが,車いすユーザーはエレベーターがある出入口しか利用できないということがある。そういった社会による配慮は,車いすユーザーを疎外し,健常者に向けられているということについて自覚できない構造がある。
特権を自覚することが社会心理学的理由は3つあるという。第一に,優位集団に属する人は,集団の一員ではなく個人ととらえるため,集団としての立場や地位がみえない。第二に,男性医師は「医者」と呼ばれるが女性医師は「女医」と呼ばれるように,優位集団は無標であり,劣位集団は有標であることだ。無標であることは,「標準」であるという無意識の刷り込みが生まれる。第三に,優位側は自らを不利な側と比較することが少ないことである。特権性を多く有する側には,特権性を有していない人が視野に入らない。こうした特権性に関する議論を日本における多文化共生の落とし穴を少しずつ可視化させ,正していくための具体的な方法かつ視点として深める必要性があるだろう。
3.共に生きる未来へむけて
1)「安心できるスキマ」を確保する
総務省が提示した多文化共生の概念とは,①互いの文化的ちがいを認め合い,②対等な関係を築こうとしながら,③共に生きていくこと,であった。マイノリティの側からこの概念を照らし出すならば,最も困難であるのは②対等な関係を築くことである。①互いの文化的ちがいを認め合うことはそれほど難しいことではない。しかし文化的ちがいが競合関係に置かれる際には,特権性や集団間の優位性がマイノリティにとって不平等な結果をもたらしてしまう。
カナグスク金城さんの語りには,多文化共生社会の実現において対等な関係を築くための重大なヒントがあった。カナグスク金城さんが多文化共生という言葉に対して創造した「異和共生」という言葉には,「自分たちが安心できるスキマを生み出し,その中で関係性を生み出す」希望が込められている。カナグスク金城さんが長い年月をかけて「安心できるスキマ」について言語化したプロセスは,マイノリティが「安心できるスキマ」を持っていないことが表れている。さらにマジョリティのみならず,マイノリティ自身もまたその事実について気が付くことが困難であることを示している。
異和共生という言葉を使うことによって,自分たちが安心できるスキマを生み出し,その中で関係性を生み出すことができると考えています。
マジョリティがマイノリティを自分たちの都合のいいように理解し,都合のいいマイノリティをつくり出すための欲求を感じ始めました。日本人が,沖縄と日本の違っている壁を壊しにかかるということです。だから,日本人が自分たちの沖縄の中にずかずかと入ってくる感覚を持ち始めました。
(カナグスク金城さんのインタビューより)
カナグスク金城さんにとって,多文化共生に対して提起した異和共生という視点の導入はマジョリティ側の都合と欲求を回避する手段であった。「文化的ちがい」がもつ壁が,マジョリティ側に壊されているという感覚。それはマイノリティを都合のいいように理解し,都合のいいマイノリティを作り出すことにつながっている。このときのマジョリティ側の振る舞いは,その個人の人格や倫理観によるものではない。自らの特権性について学ぶ機会がなかったことや,互いの違いの理解の不足によるものである。それぞれの個人が,人格的に至らないからだとか,差別的であるからではない。
だからこそ,異和共生の概念と,二つの壁のあいだの「安心できるスキマ」の確保は,「互いのちがいを認め合い,対等な関係を築き,共に生きる」という多文化共生を実現するために有効な手段である。対等な関係であるかを見極めるには,すでに特権を持っている側ではなく,疎外されている側がその関係性を対等であるとみなしているかが重要であろう。そしてマイノリティがその表明を安心して行うためには,マジョリティ側に一方的に境界を侵犯されない空間である「安心できるスキマ」を創造しつづける必要がある。
2)誰もがカラフルに生きることができる社会
以上のことは,他の多くの課題に対して示唆的である。マジョリティ特権につい参照した2章3節でも述べたとおり,特権性を持つということは自ら気が付くことができないことを意味している。本稿では,民族・人種的マイノリティについて論じてきた。しかし,属性を変えればその特権性と疎外性は異なる様相を呈する。民族・人種的マイノリティが,別の構造においては特権的な立場を持つ場合もある。これまで黒人女性によるブラック・フェミニズムマイノリティ女性によるジェンダー論などによっても明らかにされてきたとおり,マイノリティ男性がマイノリティ女性に行使してしまう暴力もある。
アビリティ(障がいの有無),ジェンダー,セクシュアリティ,階級やグローバルノース/サウスといった国際的経済格差において,誰もが特権性をもち,誰もが疎外されている。大切なことは,それぞれの特権性の自覚よりも,まずは一人ひとりが自らの疎外について十分に自覚することではなかろうか。自分が被る疎外を無視してしまう人は,他者の疎外についてもなかったことにしてしまう。「みんな我慢しているのに,なぜあなたは権利を主張するのか」というような表明の裏側には,自らの疎外を十分に表明できなかった背景がある。自らの疎外について思考できない人は,他者の疎外を認めることができず,よって自らがもつ特権性についても自覚することができない。
カナグスク金城さんの語りからは,われわれの知らない日本社会の姿が浮かび上がっている。このような語られることを待っている物語は,われわれの社会に無数に存在している。物語が内包する傷や痛みを多文化共生社会の実現のための契機と受け取るか,それとも,傷や痛みを軽視し「文化的なちがい」が存在することを妨げてしまうのか,それはこの社会で生きる一人ひとりがどのような社会を展望するかにかかっている。「和をもって貴しとなす」という日本の文化と信念は,お互いへの思いやりやケアの思想を育むことに寄与する一方で,一人ひとりの彩りを塗りつぶしてしまう危険性もはらむ。彩りを奪われた人や,自分の傷を弔うことから阻まれた人は他者の彩りや傷を尊重することができないからだ。
多文化共生社会の実現は,誰もがカラフルに生きることができる社会をもたらすと信じてみたい。人間一人ひとりがもつカラフルさとは,その人の歴史性,背景や属性,固有の傷や痛み,そして社会関係における特権性と疎外性によって彩られている。多文化共生の理念とは「互いの文化的ちがいを認め合い,対等な関係を築こうとしながら,地域社会の構成員として共に生きていくこと」であった。それはまさに,一人ひとりが,自分の傷や痛みを恐れず自らの固有の彩りを大切にすることによって,他の誰かの傷や痛みと物語を尊重する社会なのではなかろうか。われわれは,共に,そのための一歩を踏み出す時間をいま迎えようとしている。
注
1 ブラック・ライブズ・マターを指す。ジョージ・フロイド氏が警官の殺害された事件などをはじめとする黒人に対する警察による残虐行為および人種差別主義への抵抗運動。