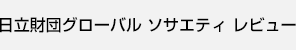『在日韓国人になる』の著者と語る多文化共生
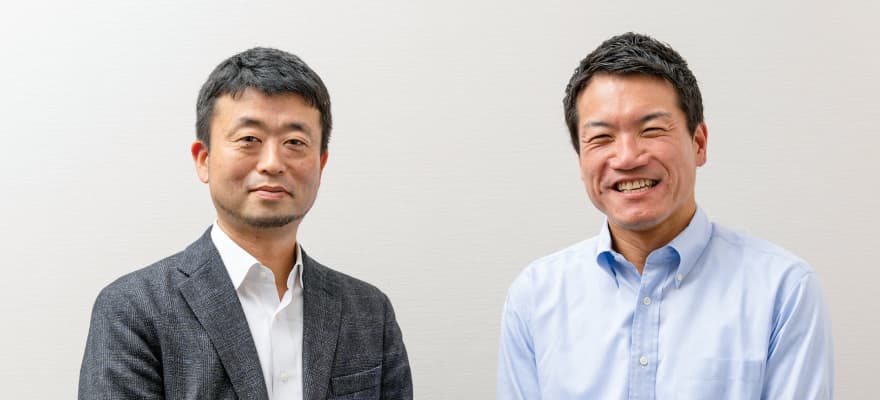
在日の歴史を丁寧にひもとき,若い世代と語り続けたい
是川:私は長年,社会学や移民研究に携わっています。この媒体では,多文化共生を切り口に,その先にある日本社会の岩盤のようなものに到達できればと思っています。今回,林さんの著書『在日韓国人になる』を読み,ヒントをたくさんいただき,ぜひお話をうかがいたいと思いました。
林:ありがとうございます。私は在日コリアン3世として,1981年に東京の江戸川区で生まれました。家庭はそれなりに複雑でしたが,下町風情が残る地域に支えられましたし,日本の公教育の下で大きな民族差別を経験することもありませんでした。とても幸運でしたね。慶応大学に進学したあと,「いつかは日本国籍を取るんだろうな」と思ってもいました。ですが,2002年の小泉訪朝後,第一次ヘイトスピーチともいうべき波が来ます。日本国/国民に拒絶されたという被害者意識が強くなって,第三の道として“韓国籍”を取ることにしました。現在は,私立の中高一貫校で教師として働いています。
是川:そうしたいきさつが,ご著書『在日韓国人になる』にも詳しく書かれていますね。本の出版に至った経緯には,どんなことがあったのですか。
林:『アステイオン』という雑誌から執筆依頼を受け,国籍変更の経緯を書いたんです。「“朝鮮籍”は厳密には国籍ではない」といった話をはじめ,若い読者にも分かってもらえるように配慮しました。すると多くの方に評価していただき,この文章を発展させて一冊に仕上げました。今では在日コリアンの歩みを一切知らない若者も多いので,韓流に憧れるティーンエイジャー向けに,その歴史を示したいとの思いが強かったですね。在日は,1970年代までは確かに排除されていましたが,その後90年代まで30年弱の間は,いわば“統合の時代”に入りました。けれども2000年代になり,再び排除の時代となってしまった。この本では,「日本社会は在日の統合に一度は成功しているのでは」と問題提起しました。大胆に言えば,70〜90年代の30年弱というのは,これから移民をより多く迎える日本にとって一つの成功体験と位置づけられるのでは,ということです。
是川:従来の在日の歴史研究では,林さんがおっしゃる“70~90年代の30年間”はどのように書かれてきたのでしょう。

林:「指紋押捺廃止をはじめ差別的制度の改善は進んだが,それでもなお深刻な差別は残った」とされやすいのではないでしょうか。たとえば,1980年代に多く見られた「本名宣言」(通称名を放棄して本名を名乗るという宣言)にしたところで,会社に入ったあとは通称名に戻す在日コリアンはたくさんいました。日本社会には在日を下に見るという図が根強くあるから,「警戒心は怠るな」といった言説も優勢でしょう。ただ,警戒心を怠るべきでない相手は在日コミュニティ“内”にもいたのでは,という思いが私にはあります。
是川:確かに,日本社会も一枚岩ではないし,在日と一括りにされるなかにも,いろいろな分断線が走っています。林さんは日本社会と在日コミュニティの両方を俯瞰して見るという視点を設定したことで,両方の変化と多様性が見えて,そのなかで,違和感や取り残されている感を持っていたのかもしれませんね。
林:そうですね。在日には,民族学校でエスニシティに基づく誇りを培ってきた人がいる一方,日本の公教育の下,それとは別の歴史を歩んできた人もいます。実は後者のほうがマジョリティーだろうとも思います。自分の経験に照らし合わせながら,これまで顧みられにくかったその人たちの歩みをたどってみよう,との問題意識もありました。
特別永住者の数の減少と在日にとっての国籍
是川:私の研究のなかで在日コリアンに言及するときは,特別永住者の統計が唯一のデータなのですが,80~90年代ごろから毎年1~2万人ずつ減っていて,今では30万人を切っています。これは日本に住むベトナム人より少ない数字です。外国人のほとんどが在日コリアンだった時代からすると,考えられない数字ですね。
林:一世,二世は本当に苦しんできましたし,生活保護受給率が高いと言われます。他方,三世以後となると,生活水準や差別はだいぶ改善され,大企業に入ることも珍しくなくなりました。すると「国籍だけがずれている」と考える在日も多くなり,アイデンティティと生活スタイルに国籍を合わせる形で日本国籍を取るわけです。さらに,在日と日本人の間に生まれた子どもの大多数は日本国籍となります。そうしたことと特別永住者数の減少は,密接につながっているでしょう。
是川:国籍だけがずれているというのは,一方の立場の究極的な見方かもしれないけれど,それでもやはり国籍はただの記号ではありません。林さんにとって国籍とは,どういう意味を持つものですか。
林:それは本当に難しい質問で,明確な答えはまだ出ていません。万が一“朝鮮籍”と“日本国籍”しか選択肢がなかったら,日本国籍を取っていたかもしれませんが……。「国籍を逃げ道に使うとは何ごとだ」と,なかばジョークで言われたこともありますが,逃げ道としての“民主化後の韓国籍”が,私にとって眩しかったのは確かです。今の私は,国際的な信用度が高い韓国のパスポートを持ち,日本国籍を取らずに日本社会を半ばアウトサイダーとして眺めるという,ややもすると恵まれた地位にあります。
その一方で,政治学を修めてきただけに,帰属意識とかエスニックアイデンティティといった面も深く考えてしまいます。朝鮮半島に身を捧げるといった思いが乏しいまま韓国に属しているわけで,一抹の罪悪感を抱えながら今に至っているというのが本音です。
でも,少なからず消極的理由に基づいて韓国籍である,ということは必ずしも否定されるべきではないと思うんです。たとえばLGBTQをめぐる問題しかり,入管法の問題しかり,“普通”の日本人であれば敬遠しがちなテーマにアンテナがぴんと反応します。あいまいな立ち位置にある者だからこそ,この社会の“ヨコ”のつながりを拡張できるチャンスは多いはずだと信じています。
是川:林さんは,先ほど,統合の時代があったとお話されていますが,私自身,博士論文を基にした著書の中で「ゆるやかな統合」という言葉を使っています。それは日本の移民研究や外国人研究では語られてこなかったことだと思っています。これまで移民については,排除の歴史や実態,構造については繰り返し書かれてきました。しかし,すでに中長期在留外国人は300万人近くいて,ニューカマーのうち90万人弱が永住権を取り,そこにつながる予備群もたくさんいます。それをもってなお「統合が進んでない」という議論だけを展開していても,彼らのリアリティーはすくい取れません。いろいろな国勢調査のデータを使って統合状況を見た結果でも,ゆるやかに統合されているとしか言いようがないと思っています。
歴史から縁遠い若者とどう向き合うかは重要な課題
是川:著書のなかで林さんは,在日を開いていくためには,いろいろな可能性や新しい編成原理が依り代になってくるであろう,といったことを示されていますが,具体的には,どういったものに希望や可能性を感じていますか。

林:SNSでは,エスニックマイノリティーはじめ,さまざまな少数派が差別されることがしばしばですが,私が学校で接する中・高生は,本当につまらないゲームを上の世代がやっていると見ているようです。自分が尖ったこと,多数派の枠からはみ出るようなことをやったら,どうせ似たように叩かれるんでしょ,といった憤りとつながっているのだと思います。
彼らは,LGBTQやエスニックマイノリティーをめぐる問題に関して強いバイアスを持っていません。そうした問題についてよく知らないだけかもしれませんが,いずれにせよ知的なやわらかさを持っている子たちと接しているからこそ,私は鬱々としないで済んでいるのかもしれません。ある種の希望さえ抱いてしまいます。この国もまだまだやれるんじゃないかと。安直に絶望したくはないですからね。
是川:移民社会を考えるとき,若者は確かに大変重要な役割を果たしていますね。私にも高1の娘がいますが,多様なルーツを持つ同級生と普通に接している姿を見ると,希望だなと思います。一方で,歴史を教えていないから彼らは無垢なのであって,どう染まるかはこれからの生き方次第というところがある。そこにきちんと共有できる経験を提示・教育していくのが大人の役割だとも思います。
林:歴史を知ることは大事です。去年9月,関東大震災100年をテーマにした授業を行いました。ちょうどベトナムから高校生が授業体験に来ていたんです。日本人の中にベトナムから来た生徒が混じり,教壇には在日韓国人の私が立っていて,妙に感慨深かった。関東大震災では,朝鮮人,方言話者,被差別部落出身者らが殺されたという重たい事実があります。どうすれば誰も殺さずに,殺されずに,生きることができるかを考えた授業は,生徒たちにもある程度響いたようです。多かれ少なかれ,誰にでも“少数派”の一面はあるでしょう。そういった生徒たちと自分がいかに繋がれるかを考えることが,日々の課題です。
是川:林さんは先ほど,「日本の公教育に救われた」とおっしゃいましたが,義務教育まではモノカルチャーなところがあって,移民第二世代からはネガティブに語られがちです。教育とエスニックマイノリティーについては,どうご覧になっていますか。
林:外国にルーツを持つ子どもたちの教育は,まだまだ発展途上でしょう。そのことと,いわゆるブラック校則の問題は,水面下で連動していると私は思っています。学校が定めた画一性の高いルールの下,さまざまな面で枠からはみ出している子がいっそう排除されてしまうからです。
また,学校現場において,教壇に立つ人間のダイバーシティーがほとんど語られていないのも問題です。たとえば,日本の公立校で正規の“教諭”として勤めるには日本国籍を持つことが条件となります。たとえ日本で生まれ育っても,外国籍者は「任用の期限を附さない常勤講師」の扱いとなります。管理職になる資格も付与されません。教壇に立つ人間が多様であればこそ,多様な生徒たちの健やかな学校生活を期待できるのではないでしょうか。
エンターテイメントを通して経験を拡張し,多文化共生を“鍛える”
是川:この社会では,実存的に生きている日々の経験だけではなく,それをとらえる社会全体の集合意識ももう一つの現実をつくっています。直接経験していない範囲に経験を拡張していくためには,映画やメディアなどを通じていくしかないと思うので,エンターテイメントのつくり手なども積極的に応援したいと思っています。
林:大賛成です。朝鮮大学出身のアーティストたちが,日本とソウルを行き来しながら交流の輪を広げることもあります。美術雑誌などでもマイノリティのアート特集が出てきたりしていますね。
是川:はい。2019年に『美術手帖』という雑誌で「『移民』の美術」という特集がありました。当事者というと単純すぎますが,生きられた経験をちゃんと内面化している人がつくる作品は,他者に向かっても開かれている感じがしました。生の経験をしているから,解釈のレベルで他者と開いていけるところがあると感じます。移民研究者にも,最近ようやく留学生出身の人が出てきて,それは頼もしいことだと思っています。
最後に1点,林さんの著書のなかに「歴史のハッキング」という部分があって,私は正直驚きました。戦前の日本について,ある種の多様性をもち,戦後の同質性を重んじる議論よりも,もう少し複雑性の高い議論をしていたことについて言及しており,すごく勇気のある書きぶりだと思いました。在日論において,ここまで訴求し,踏み込むのは初めてだったのではないでしょうか。
林:歴史学を専門とする人であればきっとこういう書き方をしませんよね。私はアカデミアからやや距離があるので,思い切ることができたという感じです。戦前のさまざまな理念を在日コリアンが“盗む”という知的にスリリングな営みは,あっていいかもしれない。ただ,盗んだ結果,「日本に完全に同化します。それが幸せにつながるんです」といった教条主義に陥ってしまっては元も子もない。歴史に学びながら,何とか隘路を行けないものかと手探りし続けたいです。
今回,多文化共生についてお話しさせていただきましたが,若者がこの言葉をどれだけ知っているかというと,ちょっと怪しい。今後はこの言葉をもっと“鍛える”必要があると思います。そのことをふまえ,過去にどういう理念があったかを振り返るのはとても意味があると思います。レヴィ・ストロース流の“ブリコラージュ”,いわば理念の金継ぎだって大事かもしれません。戦前の理念に関わる議論をタブー一色にしてしまうと,かえって神聖視されてしまう恐れさえありますから。
是川:私も,多文化共生という概念を鍛えて拡張していくことは,これからの社会において,大いに必要性があることだと思っています。本日は貴重なお話,いろいろとありがとうございました。
(2023年12月21日)