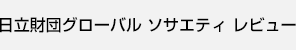ファミレス,グラス,居酒屋,ジレンマ
会話形式で,日本社会で「移民」をテーマに創作をすることについて考えることを,自由に書いた。自分の背景,「移民」をひと括りにしてしまう危険性,「移民」をテーマにすることのジレンマ,自らが想定する観客(鑑賞者)の興味の範囲など,話は脱線しながら,だらだらと進む。なるべく平易な言葉遣いで,日常の会話をベースに書くことを意識した。創作をするときにわたしが最も気にすることとして,「他者のことをできるかぎり自らのことと考える(けれど他人の物語を自分のものにしない)」ということがあるからだ。
登場人物
A・・・是川夕,国立社会保障・人口問題研究所国際関係部長,日立財団グローバル ソサエティ レビュー編集委員長
B・・・神里雄大,劇作家,舞台演出家
雑居ビルの2階。某ファミリーレストラン店内。窓側の4人がけの席に,テーブルを挟んでA,Bが向かい合って座っている。QRコードでの注文を済ませ,ふたりともドリンクバーを取りに行き,帰ってくる。Aはアイスコーヒー(グラス)を,Bはホットコーヒー(カップ)を持ってくる。
A「神里さん,改めまして今日はよろしくお願いします」
B「是川さん,こちらこそよろしくお願いいたします」
Aは,Bに名刺を差し出す。
A「ちょっと変なタイミングになりましたが」
B「(名刺を受け取りながら)ありがとうございます。……あのう,すみません,僕の名刺は家に忘れました」
A「大丈夫ですよ。以前,神里さんの舞台見てます」
B「あ,そうなんですか。ありがとうございます」
A「実はけっこう前から知ってまして,何年前かは忘れたんですがけっこう前に,雑誌のインタビューで,移民とかご自身のペルーの話をしていたのを見て,ああ,こういう人もいるんだって思って。それから,あれはコロナ前だったと思うんですけど,横浜で琵琶湖のやつを見ました。外来魚の」
B「あ,そうなんですか。ありがとうございます。『ニオノウミにて』ですね」
A「はい,あと去年くらいにやっていた『イミグレ怪談』も行ったんですよ。幽霊が移民するやつ。年末でしたっけ? 映像になっちゃいましたけど」
B「ああ,そうですね……。コロナで,最後のほう上演できなくなっちゃって……。それはすみませんでした」
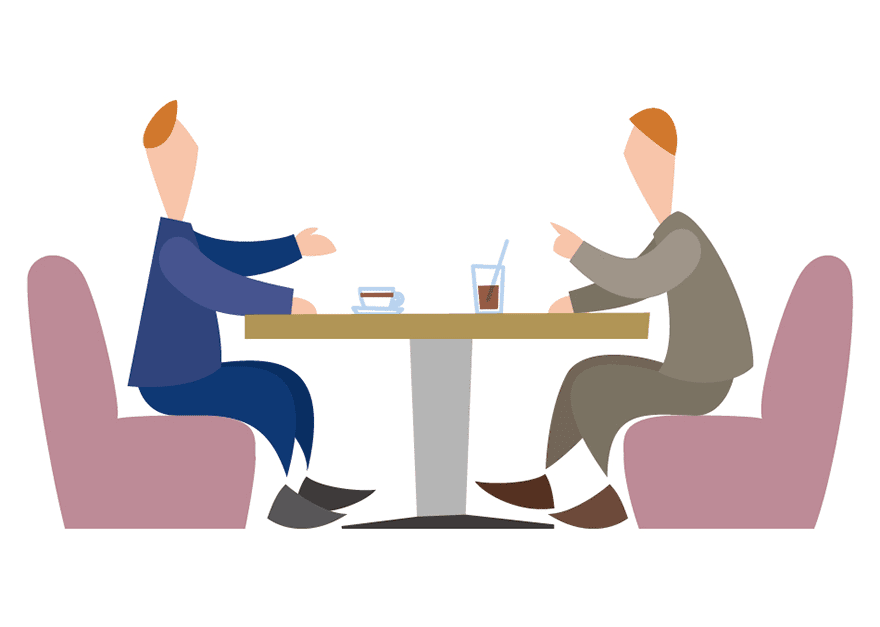
A「いえいえ」
B「あれは,けっこうしんどかったですね……。というか,コロナもそうなんですけど,(東京)オリンピック以後,(国の)文化予算が減ってるのか知らないですけど,正直助成金とかどんどん悪くなってまして。なかなか厳しいです。
そもそも,移民をテーマに,とかやってますが,日本でやっても誰も興味ないんじゃないの? って思いながら……やってます」
A「なるほど」
沈黙
A「それでメールでもお伝えしたんですけども。日立の財団で,グローバルソサエティレビューっていうのをやってまして」
Aは,冊子を取り出し,Bに見せながら,財団やその事業の概要,ジャーナルの説明を一通りする。Bはそれを聞きながら,時折「はい」などと相槌を打ち,コーヒーを飲む。
A「第3号は多文化共生とアートがテーマで,それで神里さんのことを思いついたという感じですね。その,これは僕の印象なんですが,日本において,移民をテーマにした作品って増えてきているとは思うんですけど,ただ日本では,……ちょっと表現難しいですが,抽象度が高い表現が多いと思うんです。いっぽうで諸外国では,社会における移民の問題というのが一大テーマになっていて,アートもそのことをダイレクトに表現しているように感じるんですが」
B「たしかにそうなんじゃないかと思います」
A「はい。でも,それに対して,日本だと印象というかフィクション性が高いというか。実際,神里さんの作品も,フィクションに重きを置いているという感じですよね。それはもちろん,良い悪いの話ではなくて。僕が思うのは,まだ日本社会においては,移民,あるいは移住するということをアートとして扱うにあたって,表現の枠組み自体ができあがっていない。つまり,むしろこれから作られていくという,その最中にあるんじゃないかと。それで,神里さんには,今後,というかいまの日本社会で,移民を表現することについてどういうふうに考えているのか,どのような可能性があるのか,ということを書いていただきたいと思っているんです」
Bは俯いてコーヒーを飲みながら,話しているAの手元に目線をやっている。
A「神里さんが言うように,日本社会では移民に対する関心がまだまだ低いというのもあるかもしれないですけど。もしくは,古いステレオタイプのままで止まっている。……ちょっと抽象的な話で申し訳ないんですけど,どうでしょうか」
沈黙。Bはスマートフォンを操作している。
A「……神里さん? 大丈夫ですか?」
B「あ,すみません。(目線をAに戻して)そうですね……。うーん。
あの,ちょっと話ズレると思うんですけど,是川さんの話をいま聞いていて,まず思ったことなんですけど,日本で移民って言うと,いやたぶん欧米でもそうだと思うんですけど,『移民』て外から内に来る人のことを指してますよね。日本に謎の外国人たちが働きにやってくる,それでなんか不気味,みたいな。その逆,日本から外に出ていくということについては,ぜんぜん念頭には置いてないなって。つまり自分たちが移民になる可能性のことです。過去を見ると,歴史的に日本は移民を輩出していたわけですけど。うちの家系もそうですし。
僕も混乱するんですけど,英語だとimmigrationとemigrationとがあるじゃないですか。いま調べたんですけど,immigrationは入国,つまり来る移民のこと,emigrationは出国する移民のことみたいですね。でも,日本語だとどちらも移民という単語になってしまうじゃないですか。だから……,
あの,ちょっとすいません,コーヒーお代わりしに行ってきていいですか?」
Bはドリンクバーコーナーへ向かう。数分後戻ってくる。
B「すみません,時間かかりました。
……あの,ちょっと考えていたんですけど。なかなか難しいなって思いました。
たとえば日本社会でどう移民のことを表現するのか,とか,是川さんの言うとおり,日本社会では移民ということに対してイメージが漠然としている感じがあるのもわかりますし,これは僕の実感として,さっきも言いましたが,全然興味ないじゃんていう。僕の身の回りの人だけかもしれないですけど。でも逆に,興味がある人たちは,同じような問題意識を持ち寄って集まって,それを身内で交換してるだけじゃないの? みたいにも感じちゃったりして。ちょっと意地悪な言い方ですけど。
じゃあ僕はなんで,それをテーマにやっているんだろう,ってことなんですけど。ちょっと気づいたことがありまして。それがなにかというと,さっきから僕は移民を『テーマ』に,と言っているんですよね。そして,是川さんは『移民』を扱うと(言っている)。もしかしたら,それってけっこうな差なのかもしれないなって思いました。僕はもしかすると,移民そのものへの関心がそこまであるわけじゃないかも,とさえ思いました。もう少し考えてみたいと思うんですけど,たぶん前提? あるいは根底にしているものが,そこではないというか,違うところにあるような気もしました。うーん,うまく言えないですね……。
そうですね,それには,まずは,……正直いろんなところで聞かれるし,話もしているし,自分ではやや食傷気味なところが否めなくてためらいがあるんですが,でも,その『前提のこと』を話すうえで,まずは,僕自身のバックグラウンドを話さないといけないような気がしてます。ということで,恥ずかしながら以下,僕の話をします……」
Bの一人語り
B「僕は1982年,昭和57年,の7月にペルーのリマで生まれて,生後半年で日本に来ています。母親は札幌生まれ札幌育ち,父親は沖縄の,たぶん那覇生まれで,小学校1年生を終了してペルーに渡ってそこで育ちました。あ,これ(カップ)が母親で,すいませんちょっと借ります,これ(グラス)が父親です。
なんで父親(グラス)がペルーに渡ったかということですが,というのも,これ(フォーク)を父方の曾祖父としますが,つまり僕の父親(グラス)のおじいちゃんが,1920年に,だからもう100年以上前ですが,沖縄からペルーに移民したんですね。えーと,これ(冊子)をペルーとしますね。で,沖縄をこれ(紙ナプキン)で。えーと,札幌は……まだいいかな」
テーブルに置いた冊子の上に,Aのグラス,フォークを置いていく。以下,そのような調子で,テーブル上にあるもの(グラスやカップ,ナイフやフォーク,自分のスマートフォンなど)を使って,人物マップを作り,指差しながら話していく。
B「当時は移民船で,数ヶ月かけて行ったみたいですね。そしてその数年後に,この,曾祖母(ナイフ)がおそらく曾祖父(フォーク)からの呼び寄せでペルーへ行った。曾祖母(ナイフ)の移民の詳しい経緯はよくわからないけど,JICAの移民データベースを見ると移民当時には,すでに神里姓を名乗っていたようです。なので,曾祖父(フォーク)と曾祖母(ナイフ)は沖縄ですでに結婚していたんじゃないかと思うんですけど。
それで,ペルーで祖父(Bのスマホ)をはじめ数名の子どもが生まれました。祖父(Bのスマホ)は1928年生まれだったけど,長男だったことから,沖縄の教育を受けさせるという両親(ナイフとフォーク)の方針で,1940年ごろに沖縄へ送られ,曾祖父(ナイフ)の兄である曾祖伯父(Bのボールペン)の家に住んだんだそうです。僕の祖母(スプーン)は,曾祖伯父(ボールペン)の家のごく近所に住んでいて,来沖当時まだ12歳だった祖父(スマホ)とは同い年で,きょうだいのように育ったと聞いています。そして戦争が起きて,そのまま,祖父(スマホ)たちは沖縄で終戦を迎えました。17歳のときだそうです。
で,戦後に祖父(スマホ)と祖母(スプーン)が結婚して,父親(グラス)が産まれて。祖父(スマホ)は沖縄で仕事をしてたんですけど,ペルーの曾祖父(フォーク)からそろそろペルーに戻ってこいと。やっぱり祖父(スマホ)は長男ということもあって,祖母(スプーン)と父親(グラス)と,そのころ生まれたばかりの叔父(塩)を連れてペルーに戻った。このときは飛行機で行ったみたいなんですけど,1956年のことだと思います。ちなみに,祖父(スマホ)は日系人の数え方で言えば2世になるんですけど,祖母(スプーン)と父親(グラス)と叔父(塩)は沖縄生まれで渡航しているので,1世ということになる。僕はちなみに世代的には4世なんですけど,数え方的には2世になるんですかね。日本育ちなので,日系人だとは言えないと思いますが。
で,父親(グラス)は7歳からペルーで育つわけですが,現地の学校に通ってスペイン語を習得して,それで20歳くらいのときだと思うんですけど,日本に留学してきて,なぜか北海道大学に行くことになったらしいんです。それで札幌出身の母(カップ)と出会って,やがて結婚して,でもやっぱり父親(グラス)も長男だったんで,母(カップ)を連れてペルーに戻った。そしてようやくそこで僕が生まれるんですけど,ペルーの生活に母(カップ)は慣れなくて,すぐに日本に戻ってしまった。父親(グラス)も後から付いてくる。という感じです」
Aは混乱している。
A「……なるほど」
B「わけわかんないですよね」
A「そうですね,これ(グラスなどを指す)で余計にわからない気もしますが……(笑)」
B「要するに,沖縄とペルーを行き来してる感じです。曾祖父は沖縄生まれ,祖父はペルー生まれ,父親は沖縄,僕はペルーです」
A「交互なんですね」
B「はい。でもまあ,それはいいんですよ。よくわかんなくても。でも,これは,もう方々で言っているというか愚痴ってることなんですけど,日本で,初対面の人に出身地を聞かれるとするじゃないですか。そしたら,ペルー生まれですって言うじゃないですか。すると,だいたい『ハーフなの?』って言われるんですよね。『ペルーの血が入ってるの?』って。体感9割はそんな感じです。だから最初は,毎度毎度こういう説明をしていたんですよ。でも,どうせよくわかんない。すぐ『血』の話になるんで,説明するけど,何度も繰り返ししていると,説明『させられている』気になってきてうんざりして。相手は,あいさつくらいのつもりで聞いてくるわけだから,悪意があるわけじゃないと思いますけど,何度も聞いていると,まあ鬱陶しいですよね。最近は本書いてるからそれを買ってくれ,とか言ったりもしますけど。とにかくめんどくさいっていうのが最初にあって,めんどくさいがやがて,またかよ,勘弁してよってなっていく。
……それでですね。前提としていま話したようなことを説明したうえで,問題というか,誤解というか,思い込み? がいくつか生まれます。
まず,ぼくはこのとおり,顔が沖縄顔なんですが,ペルー生まれと言うと,『ああ,なるほど』って言われる。これは日本だけじゃなくて,外国でも,『お前顔が日本人ぽくないって思ってた』って。でも,いやいや,違うよ,いま説明したじゃん。ペルーは関係ないんだよ。けっこう典型的な沖縄顔なわけ,たぶん。……典型的な沖縄顔っていうのも,その言い方どうなの? って,いま言いながら思いましたけど。まあそれはいまはいいです。とにかくこれが1個目です。
2番目。やっぱりね,バイリンガルだと思われるんですよね。
だけど,専業主婦だった札幌出身の母親に育てられて,日本の学校に通ってたし,父親も沖縄育ちの祖母に育てられたので日本語がネイティブだしで,僕はスペイン語はうまく話せません。むしろ勉強したのは,30代になってからです。でも,なぜかバイリンガルじゃないっていうと,がっかりされたのか? みたいな空気になったりして,いやいやいやいやなんでよ! って思うけど,でも同時にちょっと申し訳ない気持ちになる。期待に応えられずすみません,みたいな。このへんは,多少日系移民のことを知っている人からしたら,まあそういうのあるよね。沖縄の移民多いしね,とかなるかもなんですけど。
さらにめんどくさいなって思うのが,家は神奈川の川崎市にあったんですよ。で,そう言うと,今度は日系移民のことを知っている人からしたら,『ああ,なるほど』ってなるんです。川崎には日系ペルー人たちのコミュニティもあるよねって。ああ,すみません。そのとおりです。でもね違います。うちは,父親の仕事を札幌で見つけるのが難しかったから東京に来て,通勤圏の川崎に住んだだけで,父親を含めたうちの家族は,日系コミュニティとの関わりはなかった。
人はどうして他人をカテゴライズするのか?
そのステレオタイプに当てはめようとするのか?
そしてそれに当てはまらないとがっかりしたような顔をするのか?
……とか言ってみます。でもね,……なんかデモデモ言ってますけど,でも僕はペルー生まれで,ペルー国民の権利もあるんですよ。だから,ハーフかどうかって言われて,適当にごまかすのも,それはそれで納得いかないわけです。いや,納得いかなくなった,というのが正しいかもしれないです。めんどくさいし,カテゴライズは鬱陶しいけど,だからと言ってまともに取り合わないのも違う気がする」
Bはコーヒーをひとくち飲む。
B「あの,是川さん,お腹すきませんか?」
A「ああ,いいですよ。(ここでなにか)食べましょうか」
B「あの,よかったらどっか飲みに行きませんか? 時間ないですかね?」
A「ああ,そうですね。2時間くらいだったらいいですよ」
B「ありがとうございます。なんか食べたいものとかありますか?」
A「神里さんの話を聞いていたら,沖縄料理食べたくなりましたね。近くにありますか?」
B「ちょっと歩きますけどありますよ。行きましょう」
ふたりは店を出て,近場の沖縄居酒屋に入る。カウンター席に座り,オリオンビールとつまみを何皿か注文し,すぐに出てきたビールをふたりは飲む。
B「空きっ腹で飲んだのでやや酔ってきた気がします」
A「え,早くないですか?(笑)」
B「すみません。大丈夫です。気分的な問題です(笑)。でね,是川さん,聞いてください。要するにね,さっきの話ですけど,僕は移民当事者じゃないんですよ。つまり日系人とは言えないと思ってるんです。移民したのは僕の親だし,先祖だし,僕は赤ちゃんのときに日本に来ただけ。ペルーで生まれただけです。
だけどまあ,一般的な? 日本人からすれば,ちょっと違う,かもしれない。珍しいんでしょうね。自分からしたら珍しいとは思いませんけどね。だって,それがそうだったんだから。でも,そんなことにいつだったか気づくわけです。あ,ペルー生まれって全然一般的じゃないんだな,って。たぶんこういう飲み屋だったり,大学でいろんな県からの人と知り合って『どこ出身?』みたいな話をするようになってからだったかもしれないし。もう忘れましたけど,たぶん20歳超えてからです。気づいた,というか,気になり始めたのは。
そのころには演劇をやってました。大学に入ってから始めたんです。でも,僕の作品に移民のことが登場するのは,……えーと,27,8歳くらいからだったと思います。それまでは,自分の身の回りのこととか,気になること,考えたことを作品にしてました。たしか,中学時代の同窓会があったんですよ,川崎で。川崎って言っても,あれです,山の方です。川崎でイメージされる川崎って川崎駅のほうで,海側の南部ですけど,僕は北部の山側です。まあどうでもいいですね,それは。それで同窓会に行ったら,10年ぶりくらいに会う人たちがたくさんいて,そのころになるとみんな会社員してて,車買ったり子どもできたり家買ったり財布にいろいろ入ってたりするんですよ。飲み屋での振る舞いも妙に貫禄出てきてる感じです。そんなの目の当たりにしたら,正直言ってですね,なんか引け目感じちゃって。こいつらなんか順風満帆なレールの上を走る電車みたいになってるけど,俺はなんなんだって。この人たちに演劇やってるよって言うのなんかためらうな,って思ったんです。いつまでも,等身大の視点でやってる場合じゃないかも。もっと意識高いことやらないといけないかも,って」
A「……へ,へえ。」
B「それでなんだかしばらく落ち込んじゃって,そしてやる気を取り戻して,浅はかにも,じゃあ意識高いことってなんだなんだ? そうだ,社会の役に立つことだって考えて。つまり僕は,大学を卒業してからも演劇を続けていたけど,でもひそかに,これ(自分の作っている演劇)がなんの役に立つんだ? って思ってたってことなんですよね。
だから,自分も社会の役に立ってると言えそうな作品やろう,って思った。社会という海に船を漕ぎ出そうみたいな。めっちゃバカみたいじゃないですか? でも,そのときは移民の話じゃなかった。たまには出てきたかもしれないけど,メインじゃなかった。というか,移民の話をやろうと思ったのは,もしかすると最初は自分なりの戦略だったかもしれません。日本ではあんまり関心ないかもだけど,ヨーロッパだと移民の話たくさんやってるじゃんていう。30歳になる前後くらいから,外国にも自分の作品が呼ばれたり,呼ばれる可能性を感じたりし始めてたっていうのもありました。だから,そういえば,俺ペルー生まれじゃん,みたいな。使えるもんは使っちゃおうって。そのあたりで,自分がペルー生まれだってことも強調するようになったような気がします。プロフィールにわざわざ載せたりして」

Bは酒をあおる。Aはすでに3杯目を飲んでいる。
B「なんかけっこうぶっちゃけ過ぎてる気がします……。でも,そうやって自分の属性を発見して,自分でラベルを貼るようにしはじめてから,どんどん,気になりはじめたんですよ。あれ,みんななにも知らないじゃんて。ていうかみんな興味なさすぎないか? って。自分だってちょっと前までなにも知らずに生きてたくせにね。日系移民の歴史を調べたり,実際に中南米に行くようになったり,あとペルーにまだ祖母がいるんですけど,何十年ぶりに会いに行ったりして,そうやって,自分が日系人であるっていう意識を後付けで獲得した。いや,そんなつもりになっていったって言うほうが正しいですけど。とにかく,自分の身の回りに,そういう『意識高い』ことやってるやついないしっていう,妙な自意識を育てていって,で,飲み屋とかに行って初対面の人に『ペルーの血が入ってるの?』とか言われて,またかよ! ってなるという。こういうふうに言うとめちゃめちゃ厄介ですね……。
それを繰り返していって,もう後に戻れない。なまじ,後付けの感覚だから,だからこそ,まわりの『わかってくれなさ』にうまく対処できないし,うまく対処するってなんだよってなる。僕もいろんなところ行って,いろんな日系ルーツの人と会って話すと,みんな,みんなじゃないけど,ポジティブに自分のバックグラウンドを受け入れている人が多いように僕には見えるんです。それはたぶん,後付けじゃないから。そうやって,ふたつの国,ふたつの(もしかしたらそれ以上の)言葉を持っている。だから,『故郷がふたつあってラッキーだ』とか『人生を2倍楽しめる』とか言っているのを聞いて,僕からするとキラキラしてるんですよ。ああ,いいなあ! ほとんど憧れです。そうです。憧れているんです。自分もバイリンガルになりたかった。いつまでもそんなことに囚われないで,もっと自由に……。いやいや,もちろん,彼らが最初からなんにもせず自然に,そういう境地に辿り着いているはずもないんですけど」
沈黙
B「いや,ちょっと待ってください。違うんですよ,こんなことが言いたかったんじゃないです。……僕が言いたかったのは,……ひとえに,つまり,……すごいシンプルなことですけど,『移民』という人たちを一緒くたにできないってことですよ。ペルーの日系移民だって,あるいは沖縄移民って言ったって,その人たちのストーリーは人の数,家族の数だけある。そんなめちゃめちゃ単純な話です。だからむしろ,いまよりもっとフィクションに,もっと抽象的に寄ってしまいたい。
僕は片足だけを突っ込む中途半端な立場の人間です。僕にはね,ペルーのIDがあるんですよ。五反田にペルー領事館あるんですけどね,IDの住所がリマのおばあちゃんの住所のままになってるから,去年住所変更しに行ったんですよ。そしたらまず,受付で言われてることがわからないんですよ,スペイン語が。手続きの話で。留学までしたのに! なんとかがんばってしゃべるんですけど。単語のひとつひとつは聞き取れるから,だいたいなに言ってるかわかるような気もするんですけど,でも肝心のところ,細かいところがわからない。更新手続きが終わったら,レターパックでIDを新住所に送るから,送付用に隣のセブンイレブンでレターパック買ってきて,って言われてたんですけど。レターパック買うのはわかったし,もちろん買いますけど,でも,いつのタイミングで買いにいかないといけないのかが,よくわからないわけですよ。
けっきょく,領事館の職員のペルー人の人が日本語で説明してくれて,ほかにも,ここにこれ書いてください,とか,すごく親切に。それでなんとかなったんですけど,と思ったら,ペルーって義務投票制だから選挙に行かないと罰金になるんです。住所が外国(日本)だったら罰金はないらしいんですけど,僕は長年リマの住所だったから,4回分くらいかな,大統領選挙とあとなんか下院選挙かなにかに行ってないってことで,2万円くらいの罰金が溜まってるよって,その職員に言われて。クレジットカードで払えるから払ってねって言われて,わかりましたって。だから,その罰金を楽天カードで払ったんですよ! もうね,笑い話ですよ。誰にも共感してもらえない罰金を払わされたって,飲み屋の知り合いに言うんだけど,共感してもらえないから別に笑いも起きないんですよ。悔しいですよ。恥ずかしいですよ。日本語で説明されて,権利と義務だけはある」
A「神里さん,けっこう酔ってますか?」
B「酔ってますが,まだまだです。是川さん,僕はそんなもんなんですよ。だから僕はたとえば,レペゼン・日系ペルー人とかやっちゃだめだし,そもそもそんなことはできないんですよ。レペゼンて言い方古いんですかね? それが自分なりの矜持でもあるんです。けっして他者の代表をしない。代表したくなっちゃうし,油断するとしちゃうんですけど,でもしちゃいけない。
すみません,けっきょくのところ自分の創作スタンスの話です,これは。僕が作ってるのは,移民をテーマにした,といよりも,移民に興味を持って,移民に近づきたかった自分が,自分のバックグラウンドを『利用』して,自分が思ったこと,自分にはこう見えたよっていうことを,やってるんです。
僕だってペルーで育っていたかもしれないけど,そうじゃなかった。自分もスペイン語を自由に操って,日本語とスペイン語とを混ぜこぜにした独特の表現をして,領事館も余裕で……,っていう,あったかもしれないことと,憧れと,そして,いちいち血のことを聞いてくる『無理解』な同胞というか日本人というか,そのなかには自分も含まれる,そういう自分たちの無知に対する恨みが根底にあるんだと思います。
僕がやっているのは,たぶんそういうこと。だから,なんか話がめちゃめちゃ最初に戻ることができましたけど,僕は移民を扱っていない,むしろ扱えない,というのが結論です」
Aは5杯目を飲んでいるが,まるで変わらない調子で話す。
A「うーん,なるほど。なんとなくわかったような気がします。でも,そのうえであえて言いますけど,神里さん。それでは,極端に言えば,世の中の誰も,あるテーマについて語ることができないっていうふうになるんじゃないですかね。誰もが自分の個別の話しかできないということになりませんか?」
B「うーん,確かに……。いや,そうなんですかね?」
A「そうかなって思っちゃいましたね」
B「どうなんだろう……。でも,僕にとっては,ということであって,それに代表するっていう行為自体を否定しているつもりはないんです。ただ,代表することでなにかはこぼれ落ちてしまうし,代表したからといって,それがすべてではないっていうことで。」
A「それはもちろんそうです。ただ,代表するとか,まとめるとか,そういう行為の重要性を神里さんはどう考えてるのかなって思いました」
B「なるほど」
沈黙
A「いまじゃなくても大丈夫ですよ,ちょっと僕も飲み過ぎました」
B「……僕は,自分がなにか誰かを代表することはできないと思っている,っていうのは変わらないと思うんですけどね,だからフィクションをやってるのかなって思います。代表はしないしできないけど,きっかけにはなりうるんじゃないかって思っています。
世の中にはこういう話もあるよ,こういう人もいるよっていう提示かな。僕が自分のこととか体験とか,もしくは憧れみたいな自意識を利用して創作しているように,見る人も作品を通じて,作品を利用して,自分の想像,他人への想像を広げていってほしいなと思います。その意味で,フィクションでいいんだと思います。フィクションだからこそ,いいんだ,と言えるかもしれません。僕にとっては,移民のことを考えることは切羽詰まったことじゃないです。もちろんさっき言ったように,日常でいろいろありますけど。人間関係にも亀裂が入ったこともあるし。お前は細かすぎる! って。
……あれ,じゃあ切羽詰まってるのかな。切羽詰まったことじゃないからこそ,つまり当事者じゃないからこそできることがあるよって言いたかったんですけど。でも,僕の場合は後から自覚していった,自分から近づいていった,という感じなので。もちろんだからと言って,その立場から表現するのが図々しいとも思わないですけど」
A「神里さんのケースも,じゅうぶん『移民』の1ケースとして認めていいんじゃないかと。さっき言われてたように,ひとりひとり物語は違うわけですから」
いつのまにかBは焼酎を飲んでいる。Aはあいかわらずビールを飲んでいる。
B「しかしあれです,自信がなくなってきましたよ……」
A「ん」
B「いや,なんか,自分の権利とか不満とかばっかだなって」
A「どうしたんですか」
B「それって逆に自分のこと認めてない感じがなぜかしますね。権利のことばかり話してると逆に! そんなことないですかね」
A「さ,さあ?」
B「移民する側にもバランスが大事なんじゃないの? となんか思いました。社会に受け入れてもらうなら。もちろん,まず,対等な立場がある,っていう前提が大事です。でも,なにをもって対等と言うのか? それこそ,個別の話と言い出したらしかたないので……すいません,なんの話でしたっけ? なにを言ってるのかわからなくなりました!」
A「はい」
B「でも,そういうときにこそ,フィクションが機能しないといけないと思うんですよ」
沈黙
B「さっきから僕,フィクションフィクション言ってますね」
A「はい」
B「フィクション大魔王」
A「酔ってますね」
B「すみません,思いついたら言わないと気が済まないタイプで……」
A「気持ちはすごくわかります」
B「ははは。是川さんもすごく眠そうですよ」
A「はい……。気づいたらたくさん飲んでいましたね」
B「僕もです」
A「まだまだ長旅ですよ」
カウンターに空いたたくさんのグラス。ふたりは船を漕ぐ。