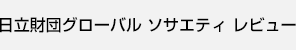編集後記
はじめまして。編集委員をさせていただいております榎井といいます。普段は,大学にいて教育社会学という分野で移民の子どもたちの研究などしていますが,地域で外国人支援をする活動も長年してきました。
縁あって毎年,関西の小学生から高校生までの移民の子どもたちの作文を読ませていただく機会があるのですが,「ことばがわからず疎外感をずっと感じていた」「自分自身の存在を気づかれないようにしずかにしていた」といったことなどが,かれらの3歳や4歳の幼い記憶の中で語られ続けていることに衝撃を覚えています。ものごころつかないうちから子どもを黙らせ,“いないもの”であることを内面化させるような社会が何十年と厳然と続いていること,その一端を自分が(この分野で活動しながらも)担い続けていることを突きつけられたからです。そんな中,昨年夏に大阪市生野区でNPOと移民の子どもたちのラップワークショップの開催を試みました。そこでは―恐れることなく表現できるサンクチュアリの場が約束された上でのことですが―参加者たちの封じ込めてきたストーリーの蓋が開かれ,応答しあう姿が見られ,刹那的ではあったのですが,沈黙をカタチにすることの重要さを実感しました。
今回の特集「Art×多文化共生」では,岩井さんのドキュメンタリー映画や,堀口さんの起業されたSOL LUNAなどでも,アートが主流社会で押し込められていた移民当事者の主体性を解き放つ重要な装置として機能する可能性が示されました。さらに神里さんの痛快な戯曲やMoment Joonさんの活動・執筆からは,本誌でもこれまでに度々言及されてきた移民に対する「受け入れ/受け入れられる」といった二項対立的な思考や,移民をカテゴライズするという発想,外からラベリングする力に抗した,捉え直しや意味の取り戻しが試みられています。アートや表現活動が,主流社会の信じて疑わないあたりまえを崩すという可能性が示されたことで,前述したような恐ろしい社会への加担からもしかしたら解放されるかもしれないという希望を感じることができました。
こうした活動を「どこにたって,どううけとるのか」。―自分のポジショナリティ,暴力性や特権性といった視点も含めて,わたしたちは問われ続けているのではないでしょうか。これからも,号を重ねるとともにこのこたえに対するヒントが少しずつ見えてくるようなジャーナルにしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。