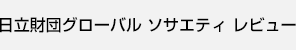Art × 多文化共生
今号のテーマは「Art × 多文化共生」です。このテーマは本ジャーナルの創刊の趣旨とも大きく重なるものであり,かなり早い時期から企画されていたものです。
創刊号の編集後記で,私は以下のように書きました。
「本ジャーナルはそうした変化をただ写し取るだけではなく,むしろこうしたダイナミズムの一部となって,新たな認識や社会の変化を促す側に回れればと思っています。この新しい現象については,まだよくわかっていないことも多いです。それは人類が月や火星に行くように,全く未知のフロンティアを開拓することと同じと思っています。本ジャーナルがそういった新たな探究の道しるべとなることを願っています。」
アートはこの新しい探求の道しるべとして最適であるという思いが,本ジャーナルの構想を練っている段階から私にはありました。それは,今号に収録された秋庭さんの論考にあるように,「『多文化』と『共生』のあいだにあるギャップを,特殊多様でありながら普遍性をもつ『アート』が橋渡しすると期待」したためといって良いでしょう。
まず,新しい試みとして,岐阜県のNPO 法人可児市国際交流協会によって企画され,高校への進学を目指す海外ルーツの若者たちの姿を映した作品「Journey to be continued―続きゆく旅」を,同映画を撮影された岩井監督の公開インタビューとともに上映しました。これは単に上映された作品を鑑賞するだけではなく,提示された作品の背景の理解も含め,オーディエンスと共通の経験をするという試みといえます。その様子は巻頭インタビューに収録されています。
収録されたインタビュー,戯曲,作品,論考も多彩です。
インタビューでは移民として日本でラッパーとして音楽活動や執筆など,多彩な活動をするMoment Joonさん,社会起業家として移民女性らによる出張デコレーション事業等を手掛ける堀口安奈さんに登場いただいています。
論考では名古屋大学の秋庭史典さんにアートと多文化共生の関係について美学研究の視点から理論的な考察をいただいています。
また,本号では通常の論文という形式にとどまらず,エッセイ,戯曲といった新しい表現形態へも対象を広げました。劇作家・舞台演出家の神里雄大さんには,私,是川と神里さん二人が登場する戯曲風のスタイルをとりつつ,日本社会で移民をテーマに創作するとはどういうことかについて寄稿いただきました。Moment Joonさんにはご自身の近著である「日本移民日記」をご自身で振り返る論考をお寄せいただきました。
いずれの『作品』においても,共通しているのは実践者,表現者としての限界と可能性,そして主体性についてはっきりと論じているという点です。
巻頭の岩井監督のインタビューでは,映画のラストシーンで監督自身が突如,劇中に現れ,一方的に若者の描いた絵を緑色の絵の具で塗りつぶすシーンの意図を,表現活動における作り手の特権性を暴くため,と説明しています。
また,神里さんもご自身が持つペルー生まれの「日本人」としてのルーツについて,周囲から期待されるイメージと自分自身の感じ方のズレについて,時に懐疑的に語っています。
このことは,堀口さんの下記の言葉にも端的に示されているといえます。
「ルーツに対する思いは十人十色でいい。そして,外国にルーツがあるからといって,そこに根差したことをやる必要も全然ありません。本当に自分がやりたいと思ったことをやるのが一番です。」
これに加え,Moment Joonさんのインタビューから浮かび上がってくるのは,移民自身の持つ主体性の重要性です。日本社会から気にかけられ,配慮される存在としての移民,外国人ではなく,みずからが発信し,表現する者としての移民,外国人という視点を読み取ることができるといえます。
「だから,このジャーナルにも頑張ってほしいけど,それ以前にまず,私たちが頑張って,もっと魅力的で,もっとセクシーで,もっと感動的なものをつくり,日本の人たちにダイレクトに届けていきたいと思います。」
加えて,多文化共生とアートという試みが持つこうした重層性を美学研究の視点から整理いただいたのが,秋庭さんの論考です。例えば,上映会の試みについては,同論考の下記の部分で指摘していることと重なるでしょう。
「互いに互いをケアし,以前とは異なる自分,互いのいずれか一方だけに属さない関係が時間をかけてわずかでも生まれてくるとき,共生に入ったと考える。このような意味での共生へと踏み出すためには,関係をつくるための場が必要である。それは,他文化の作品を一方的に見る,あるいは,教育プログラムのなかで,それについて誰かの解説を聞きながら理解するだけでは生まれてこない。アートの枠組みのなかで,共になにかを制作するといった体験が,どうしても必要なのである。」(下線,筆者)
今号の作品はどれも作り手と作品の関係を自覚的,懐疑的に捉えつつ,オーディエンスの受け止め方も含め,多層的に構成されたものですが,そういった試みがArt × 多文化共生というイシューを扱う際,まさに核心にあることを端的に整理いただいています。
最後に,こうした特徴はいずれも本ジャーナルの目的や性格とそのまま重なるものです。その意味では本ジャーナル自体が「Art × 多文化共生」の試み,作品の一つということもできると思います。
今号の企画が多くの読者の方にとって,意義のあるものとなることを願い,巻頭言としたいと思います。