�����������Љ�̍\�z�d�q�W���[�i���u�������c�O���[�o�� �\�T�G�e�B ���r���[�v��5�� �V���|�W�E��
2025�N6��15���i���j�J��
�����������Љ�̍\�z�Ɍ����āA�ږ��w�A�Љ�w�A�S���w�A�o�ϊw�A���Ԋw�Ȃǂ��܂��܂ȕ���̐��ƂƁA�O���Ƀ��[�c�������ʂȃQ�X�g���ꓰ�ɉ�āA�u����p�l���f�B�X�J�b�V�����ł̋c�_���Ƃ����Č���▢���ɂ��Č��܂��B�o�d�҂̌o����m�������L���A��̓I�Ȏ��g�݂�ۑ�����̕����T��A�����������Љ�݂̍�����l����@��ƂȂ邱�Ƃ��߂����܂��B
�{�V���|�W�E���u���^�́A�d�q�W���[�i���u�������c�O���[�o�� �\�T�G�e�B ���r���[�v��5���i2025�N12�����s�j�Ɍf�ڂ��܂��B
�uImmigrant Japan�\�ږ��Љ���{�ɂ��āv�������ʖ�iZoom�z�M�͓��{��݂̂ƂȂ�܂��B�j
�u�����O���V�A �����[ �t�@�[���[���i����c��w�����j
����c��w��w�@�A�W�A�����m�����ȋ����A����c��w�A�W�A���ۈړ������������BPh D�i�V�J�S��w�Љ�w�j�B���{�ɂ�����ږ��̌o�ϓI�E�Љ�I�E�����I�Ȏ��H�A���w���Ɛ��E�ږ��̃O���[�o���ړ��ɂ��Ď�Ɍ������s���Ă���B
��Ȓ����ɁALabor Migration from China to Japan: International Students, Transnational Migrants�iRoutledge, 2011�A�P���j�AImmigrant Japan: Mobility and Belonging in an Ethno-nationalist Society�iCornell University Press, 2020�A�P���j�AHandbook of Asian Migrations�iRoutledge, 2018�ABrenda Yeoh �Ƃ̋��Ғ��j�Ȃǂ�����B

�u��炵�Ɛ����\�������ɂƂ��Ă̓��{�A�����Đ��E�v
���f���[�^�[���� �����i������w���C�����j
������w���w������ ���C����
��U�͎Љ�S���w�B�Ό���X�e���I�^�C�v��������ߒ��A�����ӎ�����I�ԓx�Ȃǂɂ��āA�S���w������Љ����p���Č������Ă���B���s��w���w�����ȏC�m�ے��A�J���t�H���j�A��w���T���W�F���Y�Z���m�ے��C���iPh.D.�j�B���É���w���_�����A2023�`2025�N�A�W�A�Љ�S���w���B��v�����F�u�Ό��⍷�ʂ͂Ȃ��N����H�S�����J�j�Y���̉𖾂ƌ��ۂ̕��́v�i���Ғ��E���Ƃ��v���X 2018�N�j�ȂǁB

�p�l���X�g���n ���[�����X�g�F���i�����w�E�������j
���͍��ێЉ�w�B�����Ɂw�u�����v�Ɓu���{�l�v �\�n�[�t�E�_�u���E�~�b�N�X�̎Љ�j�x�i�y�ЁA2018�N�j�A�w�u�n�[�t�v���ĂȂ낤�H���Ȃ��ƍl�������C���[�W�ƌ����x�i���}�ЁA2021�N�j�B�u�n�[�t�v��C�O���[�c�̐l�X�̏�L�T�C�g�uHAFU TALK�v�������^�c�B

�p�l���X�g���� �~���i�o�D�A�^�����g�j
���e�͓��{�l�ƃA�����J�l�B��w����܂Ńo�X�P�b�g�{�[���ɖv�����A���ƌ�͎G���𒆐S�Ƀ��f���Ƃ��Ċ����B
2017�N����NHK�u�����C�`�v���T�Ηj���̃v���[���^�[�ɔ��F�����B�L�����N�^�[���������A�W�������̊_�����z���āA�f��A�h���}�A�o���G�e�B�[�A����AMC�ȂǕ��L������Ŋ������B

�p�l���X�g�}���C �����g���C�����i�R�����e�[�^�[�j
�k�h�C�c�L�[���o�g�B�m�C�G��p�`�̃h�C�c��ďC����ATV�ǃv���f���[�T�[�A�f���|��A�R�����e�[�^�[�A���M�Ƃ�H��܁E���؏܂̎�܍�i�\���܂ŁA���L������B2017�N8���ɏ�����w�h�C�c��G�b�Z�C ���Ƃ��ɂ��^�ʖڂȂ�ł��x���o�ŁB���̑��̒����́w�{���őΘ_�I ���܂ǂ��́u�h�C�c�v�Ɓu���{�v�x�i�r�㏲�Ƒ��c�������Ƃ̋����j�A�w�܂��ɂ��ӂ��h�C�c��蒠2025�x�ȂǁBJ-WAVE�uJam the planet�v��TOKYO MX�u�x�����[�j���OFLAG�v�Ƀ��M�����[�Q�X�g�Ƃ��ďo�����B�E�Ƃ́u�h�C�c�l�v�B

�u�d���ƌo�ρ\���l���ƃC�m�x�[�V�����v
���f���[�^�[���� �[���i�����Љ�ۏ�E�l����茤�������ۊW�����j
���m�i�Љ�w�j�^�����Љ�ۏ�E�l����茤�������ۊW�� ����
������w���w���A����w��w�@�l���Љ�n�����ȏC�m�ے��C����A���t�{�ɋΖ��B2012�N���瓯�������ɋΖ��B���͎Љ�l���w�A�ږ������B�o�����ݗ��Ǘ����u�Z�\���K���x�y�ѓ���Z�\���x�݂̍���Ɋւ���L���҉�c�v�ψ��AOECD �ږ��������Ɖ�iSOPEMI�j�����o�[���߂�B

�p�l���X�g�A���x���g �~�����}���e�B����
�i�c���`�m��w�y�����F��r�����_�A�ߑ���{�����j
�c��`�m��w�o�ϊw���y�����A�X�y�C���o�g�B�o���Z���i������w�|��ʖ�w�����ƌ�ɗ������A����w�ɂē��{��E���{�����̔��m�����擾�B�R��������w���ی𗬈��⓯�u�Б�w�O���[�o���n�敶���w���������o�Č��E�B���͌���w�A��r�����_�A�|��v�z�j�A���{����j�B�������e�́A�ߑ���{�ɂ����鐼�m�����̎�e�A�[�֎v�z�Ɨϗ�����A�����Ƃ̕����𗬂ȂǁB�����Z���^�[�����A���{�E�X�y�C���E���e���A�����J�w������B
�����Ɂw�w�C�g�_�x�́u�V�v�F�����ב��̖|��ɉB���ꂽ�^���x�c��`�m��w���{�����Z���^�[�ȂǁB

�p�l���X�g�~�� ���T���i������w�����F�l�ސ��Ԋw�j
������w��w�@��w�n�����ȁE�����B���͐l�ސ��Ԋw�B
�Ⴂ���́A�p�v�A�j���[�M�j�A�A�����C�쓇�ȂǂŁA�Z�ݍ��ݒ��������܂����B
�ŋ߂́A�����ۂƐl�ނ̓K���Ƃ̊W�ɋ����������A���{�A���I�X�A�G�`�I�s�A�ȂǂŃv���W�F�N�g���^�c���Ă��܂��B
�咘�́w�u�^�ƃT�c�}�C��: ���R�̂Ȃ��ɐ����邵���݁x�i���X�j�A�w�������Ƃ̋���: �p�v�A�j���[�M�j�A���n�l�̓K���V�X�e���x�i���s��w�o�ʼn�j�ȂǁB
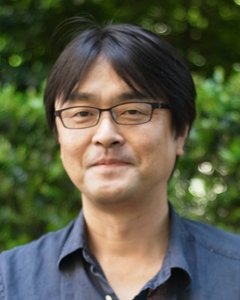
�p�l���X�g�R�`�� �I�����i�������Oyraa ��\��������j
�g���R���܂�B��w�œd�q�ʐM�H�w���U���A2006�N�ɓ��{�̃I������������Ђ̃C���^�[���V�b�v�ɉ��債�A�������B���ꌧ�������i���E�b��s�j�ŕ�炷�Ȃ��œ��{�����ɐS���B��w���ƌ�A������w�̌������ƂȂ�B13�N�ɑ�w�@�H�w�n�����Ȃ��C����A���{�Ń{�X�g���R���T���e�B���O�O���[�v�ɏA�E�B17�N�A������� Oyraa��n�Ƃ��C153�����̌���̒ʖ�҂��ɌĂяo����A�v�����J�����b��ƂȂ�B18�N�A���{�ɋA���B���݁A�������Oyraa��\������В��̂ق���ʎВc�@�l�O���l�ٗp���c�� ���������߂�B

�p�l���X�g�F�� �͓T���i�R�w�@��w�����F�u�ږ��̌o�ϊw�v�j
2002�N�W�����Y�E�z�v�L���X��w��w�@���ph.D.�i�o�ϊw�j�擾�B
���E��s��ďB�J����s�ɂăR���T���^���g���o���B�J���t�H���j�A��w���T���[���X�Z�iUCLA�j�o�c��w�@�G�R�m�~�X�g�A�s�b�c�o�[�O��w��w�@�q������������уj���[���[�N�s����w�������Ȃǂ��o�āA���݁A�R�w�@��w���ې����o�ϊw�������B�����Ɂw�ږ��̌o�ϊw�x�����V���A�w�O���l�Ƌ������邽�߂̎��H�K�C�h�u�b�N�x���{�]�_�Ђ�����B

���O�\�����݂��K�v�ł��B
�y���180�� �\���撅���z
���ł̂��Q��������]�̕��́A�u���Q���v���\�����݃t�H�[�����炲�o�^���������B
���\������A���o�^�������������[���A�h���X���ɏڍׂ����A�����܂��B
�u���Q���v���\�����݃t�H�[��QR�R�[�h

�I�����C���iZoom �E�F�r�i�[�j�ł̂��Q��������]�̕��́A�u�I�����C���Q���v���\�����݃t�H�[�����炲�o�^���������B
���\������A�ڑ��̂��ē���o�^�������������[���A�h���X���ɂ����肵�܂��B
���Q���ɂ������Ă̂��肢