認知症の人たちには色々な可能性があります。
最後に一番大きなポイントとしては、認知症になってももう隠さない、認知症になったら早く自分が認知症であることを公言していこう、という事です。そうすることで、周りからも支援を受けやすくなり、認知症になっても人生を楽しんでいけます。認知症の人が先頭になって、暮らしやすい街を一緒に作っていこうと、当事者が社会に向けて提案や政策提言をしていく認知症ワーキンググループが2014年に発足しました。海外の認知症の当事者グループと、認知症の本人がスカイプを使って交流したり、行き来をして国際的な交流の輪が広がりつつあります。国も認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)という国家戦略を掲げて、省庁を横断して認知症にやさしい地域を作る動きを加速しています。もはや認知症は医療・介護分野内のみの対策ではなく、あらゆる分野が連動したまちづくりに挑む時代になったのです。認知症を通じて、人にやさしい町になり、いろな人たちが元気になり、それぞれの力を出せる活力のある超高齢社会を作っていけると良いと思います。皆さん、お一人お一人が、ご自身の仕事や生活の中で自分でもやれることはないかなと、一緒に考えていただけたらと思います。
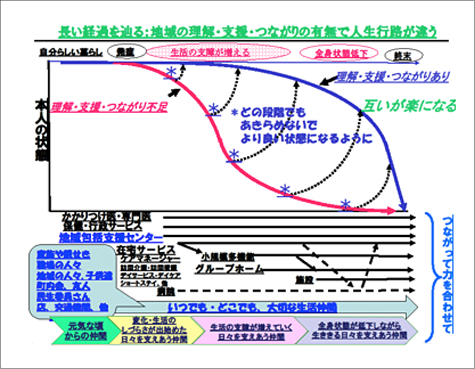
認知症になってもまだまだ外で体を動かしたいという人が一緒に走る「RUN TOMO-RROW(RUN伴 らんとも)」という活動があります。認知症の方が走りながら若者や、街の人と一緒になってタスキをつないで、認知症の人と共に明るい未来をつくっていこうというものです。毎年参加者が増え、今年は北海道から沖縄まで全国で1000人以上の人が一緒に走っています。認知症初期の人もいますし、重度で車椅子レベルの人も参加しています。本日紹介するのは、若者たちが自分たちも何かできることがあるのではないかと、この活動の映像を作り、編集したものです。この映像には、39歳で発症して、今41歳の男性も出てきます。この方は、会社の理解や支援を得て、認知症でも働き続けることに挑戦しています。認知症の人ほど実はパソコンがとても大事な装置です。記憶が自分の脳の中には刻まれないので、パソコンが外付けの頭脳として重要な役割をはたします。認知症の初期段階からパソコンを使い始めようとか、認知症の人がiPadを持って出掛けようとか、どんどん新しい技術と、認知症の人とのコラボも生まれてきています。特別な対策よりも、普通の生活の中で当たり前のことを一緒にやる、そんな場面を増やすことが、生きた時間になると思います。楽しいことを一緒にやっていると、結構若い人たちも一緒になって、若者にとってもいい時間ができているように感じます。
日本は何を国際貢献できるのでしょうか?日本は超高齢社会で世界一進んでおり、認知症の人が増えている国です。日本が失敗して来たことを輸出してはならないと思います。認知症の人は、何もわからなくなって、できなくなって、無残な姿で残念な日々を送って、いつの間にか社会から消えて行く、そのような存在では決してありません。認知症になっても、面白くも格好良くも生きられるし、貧富の差があっても、こういう地域や人とのつながりがあれば地域の中で幸せな最後を迎えられる、そんなことが今日本で始まっていて、世代を超えた若い人や子どもと一緒になったこういう動きを、どんどんと世界に伝えることで貢献できるのではないかと思っています。
RUN TOMO-RROW: https://runtomo.org/



